特別休暇の注意点と有効利用
慶弔休暇などの特別休暇といえば、多くの企業等が就業規則に定めていると思います。
付与日数や条件などが規定されていると思いますが、
いざ従業員が取得しようとするとトラブルになることもあるようです。
特別休暇について法律上必ず定めなければならないものではないですが、
従業員の方々にとっては大切な規定になります。
ご一読いただき、就業規則などについて今一度見直してみるのもよいかもしれません。
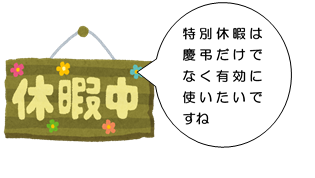
●決めておきたい付与ルール
会社の特別休暇といえば、法律上定められているわけではありませんが、
制度があるところが多いでしょう。
しかしながら絶対に定めなければならないものではないし、
その事由や日数も色々でしょう。
多いのは慶弔休暇制度が挙げられます。
年次有給休暇を使用するようになっている企業もあるでしょう。
このような休みにも、どのような時に何日くらい休めるのか
決めておかないとトラブルになることがあります。
●休暇を決める際の注意点
付与される日数だけでなく「継続か、断続か」「有給か、無給か」
等も考えましょう。
慶弔休暇と所定の休日が重なったときにはどうするのか、
例えば従業員の親御さんが亡くなり5日間の慶弔休暇が取れるとして、
土日休みの会社で月曜日から休んだ場合、
前の土日と5日取得後の土日と合わせて9日間が取れます。
しかし水曜日から取得した場合5日間はどこまでと考えるのか、
次週の月曜日から出社とするのか、本来の土日休日は含まず
次週の火曜日とするのかという問題があります。
弔意休暇であれば所定の休日は日数を消化したと考えるのが普通だと思えますが、
思わぬ解釈違いがあってはいけないので就業規則には定めておきたい事項です。
●結婚休暇も定めておく方が良いことがある
例えば従業員が結婚したときには5日の休暇を付与するとしたとき、
5日間は分割して取れるのか所定の休日は含まれるのか
などと決めなくてはなりません。
結婚してから半年、1年たって請求されるケースもありますから、
有効期限も決めておいた方がいいでしょう。
また、休暇中の賃金支払いの有無も決めておく必要があります。
●色々な特別休暇
慶弔休暇はたいていの会社にありますが
法律上はなくてもかまいません。
しかしたいていの会社にあるものがないと、
そういう会社なのだなと思われてしまいます。
特別休暇は企業が設定するものなので
有効な使い方をすることもできます。
例えばリフレッシュ休暇などで続けて休暇を取れる制度もあります。
(特別休暇ではないが労使協定で計画年休を充てることも有です。)
最近では、ボランティア休暇やコロナウイルスのための
特別休暇制度を設けると受給できる助成金もあります。


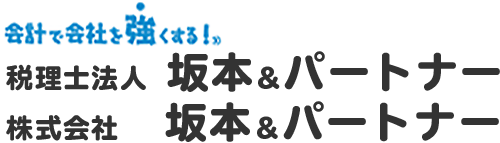
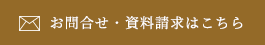
![浜松市の税理士法人 坂本&パートナー[ 静岡県浜松市 ]](https://www.hamazo.tv/img/template_img/sakamoto/mainvisual.jpg)
![浜松市の税理士法人 坂本&パートナー[ 静岡県浜松市 ]](https://www.hamazo.tv/img/template_img/sakamoto/mv/Sakamoto-Partner-01.jpg)
![浜松市の税理士法人 坂本&パートナー[ 静岡県浜松市 ]](https://www.hamazo.tv/img/template_img/sakamoto/mv/mainvisual.jpg)










